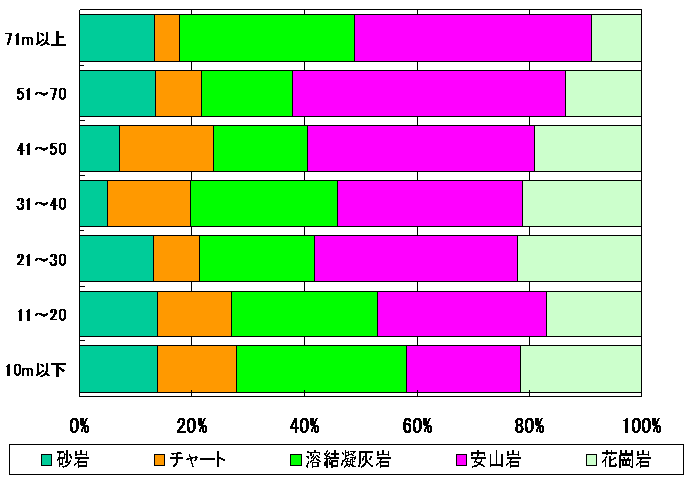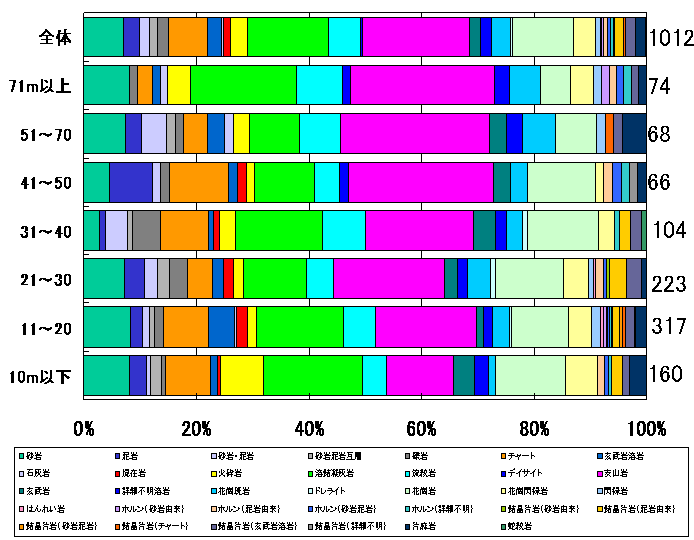|
滝の落差に影響する因子 |
滝を見る上で最も印象に残る因子は落差であろう。そこで、落差に影響する因子を探る目的で滝の落差毎に各要因の頻度を検討した。検討したのは滝の形態分類、連瀑数、標高、滝の傾斜、地質である。
検討に用いた滝は落差10m以下のもの160滝、11~20m317、21~30m223、31~40m104、41~50m68、51~70m68、71m以上74、計1024滝であった。単独瀑のみに限った場合には落差10m以下のもの127滝、11~20m250、21~30m173、31~40m73、41~50m42、51~70m51、71m以上46、計762滝であった。なお、検討によってはデータ不明の滝があり除外したため、滝数は微妙に異なった。ただし、検討滝数が多く、全体の結論には影響しないと考えられるので詳細は省略した。
なお、このページは北中康文著「日本の滝、東日本661滝1)、西日本767滝2)」に記載された滝データ、地質データをもとに行ったメタ解析の一部である。
1.滝の落差と形態分類
滝の分類としては永瀬嘉平氏の著作に紹介された分類法(直瀑、渓流瀑、段瀑などに分類。以下、永瀬氏分類とする)が最も有名である。この分類は滝の姿が人の心にどのように映るかという事に着目した心象分類と言えるであろう。簡単で分かり易く、印象深いという特徴を持つ。しかし科学的な観点からは問題が多い。
HP「滝を観る」に記載された分類(以下、滝おやじ分類)は科学的観点からみた客観的で重厚な分類である。分類法というよりも客観的な滝の記述法という色彩が強く、初心者にはやや難解である。今回はメインの分類のみを検討に用いた。
永瀬氏分類(図1A)では緑で示す直瀑は落差の変化で比率は余り変わりないが、オレンジの分岐瀑は落差が高くなるとやや少なくなる。最も大きな変化はピンク色の段瀑で見られ、落差が大きくなるに従って頻度がます。黄緑の渓流瀑、薄緑の潜流瀑は落差が10m以下で最多であり、いずれも落差が低いものに限られる。
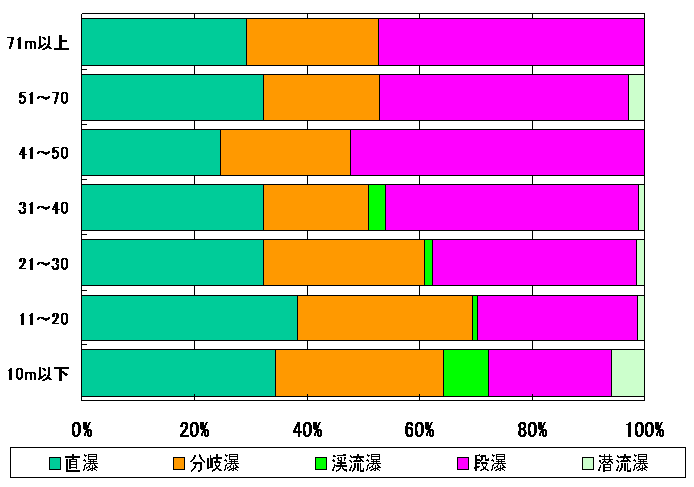
|
|
図1A.滝の落差毎にみた永瀬氏分類 |
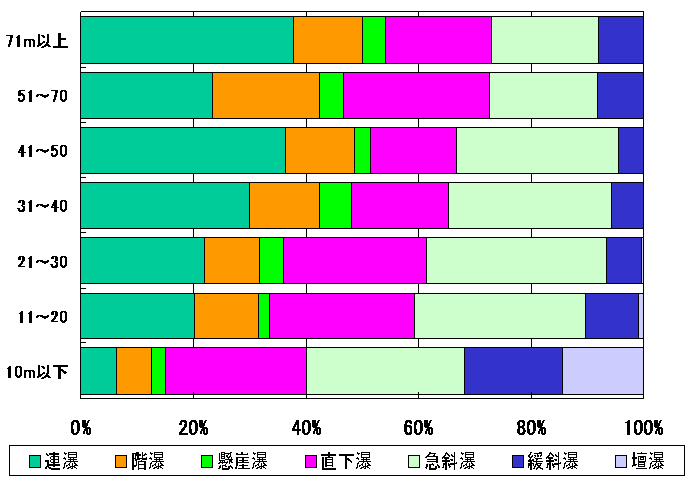
|
|
図1B.滝の落差毎に見た滝おやじ分類 |
| 2.連瀑数の比較 前項で落差が高くなるほど段瀑(図1A)、連瀑の比率が増していることを示した。それでは連瀑の数はどうなるのだろうか。 図2に落差毎の連瀑数を示した。単独瀑を1とし、二連瀑は2という要領にした。多連になると書籍からは正確な情報が得られないので、5連瀑以上はすべて5とした(本文中に連瀑数が書いてある場合を含む)。滝の落差毎の平均を棒に上に付けたひげで標準偏差を示した。 その結果、落差51~70mの所にへこみがあるが、落差が増えるほど連瀑数も増えていることが分かる。 3.滝の落差と滝の標高の関係 4.滝の落差と滝面傾斜の検討 5.滝の落差と地質の比較 全岩石(図5B)では煩雑だが、上記の5大主要岩石以外の動きを示す。 |
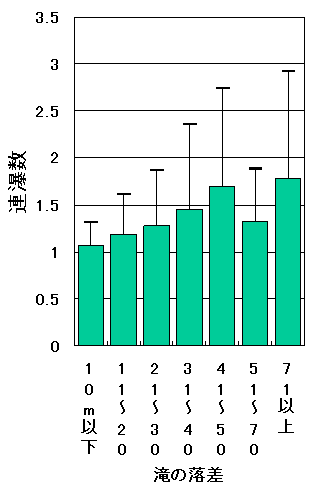 |
|
図2.滝の落差と連瀑数 |
|
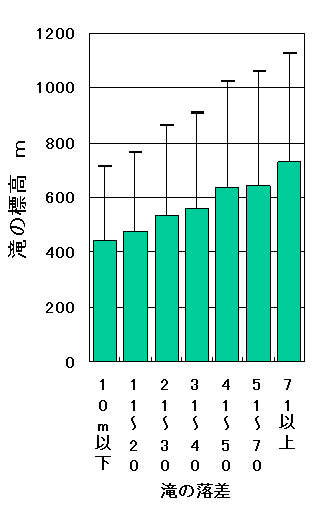 |
|
|
図3.滝の標高と滝の落差 |
|
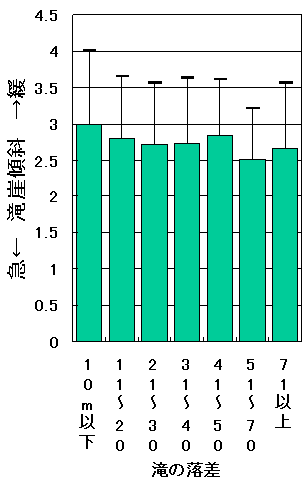 |
|
|
図4.滝の落差と滝面傾斜 |
|
|
|
|
|
図5A.滝の落差毎に見た滝の構成岩石の内訳(主要5岩石) |
|
|
|
|
|
図5B.滝の落差毎に見た滝の構成岩石の内訳(全岩石) |
|
6.地質年代との比較
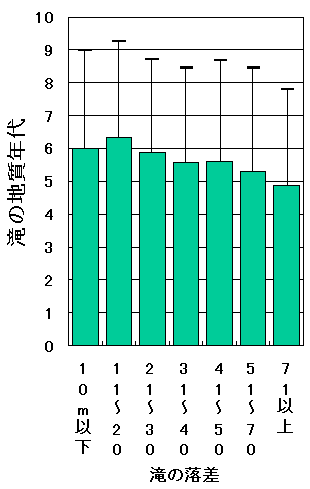 |
|
図6.滝の落差と滝の構成岩石の地質年代の関係 |
滝の落差と滝の構成岩石の地質年代の関係を示す(図6)。縦軸の下の方が構成年代が新しいことを、上の方が古いことを示す。
その結果、落差が高い滝の方が新しいことが分かる。多重比較では、70m以上の滝と10m級の滝を中心に有意差が見られた(詳細は省略)。
図5Aで示したように、形成年代が新しい安山岩、溶結凝灰岩が落差の高い滝に多く、古い花崗岩やチャートが高落差の滝に少なくなることを反映した結果であろう。
まとめ
1.永瀬氏分類では落差が高いものに段瀑が多く、渓流瀑、潜流瀑の落差は低かった。
2.滝おやじ分類でも落差が高いほど連瀑が多かった。緩斜瀑、段瀑は落差が低いものに多かった。
3.滝の落差が増えるほど連瀑数が増え、標高も高く、単独瀑の場合には傾斜も急だった。また、滝の構成岩石の形成年代も新しかった。
4.落差と構成岩石の関係では落差の高いほど安山岩が多く、低いほど花崗岩の滝が多かった。少数例の岩石では流紋岩、花崗班岩は落差の大きな滝に多く、花崗閃緑岩は低い滝に多い。
考 察
常々、当HPでは以下のように主張していた。「落差の高い滝は不安定であるので傾斜が付きやすい。一方、低瀑では構成岩石の種類によらず直瀑になりうる。」 しかし、今回の検討では、落差が高いほど傾斜が急で逆であった(図4)。
これはサンプリングの問題だと思う。高落差の直瀑は目立つので本書に掲載される確率が高かったであろう。また、高落差の直瀑には特殊な仕組みの存在も示唆されるが(例えば水平傾斜の成層砂岩)、こういった特殊な滝は採用されやすいだろう。高落差の傾斜瀑、特に緩傾斜の場合には滝と呼ばれること自体が少ないであろう。一方、低落差の滝は多数あるのに掲載されたものは一部のみで、そこにはやはり特色のあるものを掲載しようという編集意図が働くであろう。なお、これは北中氏の著作を批判しているのではない。学術的意図を持って作られたものではないのだから。それにも関わらず最も有用な著作と信じる。
と言う訳で上述の仮説を捨てるのはまだ早いと思っている。独自のデータベースを構築した上で再検討したいと考えている。
参考文献
1)北中康文(2004):日本の滝①東日本661滝.山と渓谷社
2)北中康文(2006):日本の滝②西日本767滝.山と渓谷社